『HER STORIES』上映会レポート
この映画を制作した発端は「女性は好きで派遣をやっている」発言を聞いた事だった。その発言を聞いた日から、私の中に微妙なわだかまりが生まれた。本当に女性達は自分の意志で「好きで」様々な労働を担って来たのか?それについて多くの女性達と語り合いたくてこの映画を撮った。
よくこの映画については「いわゆるプライベートドキュメンタリーですか?」と問われる。この言葉は90年代に流行した自分の実存やプライベートを露呈するタイプの私的なドキュメンタリーの事を指す。
でも、残念ながらそれは違う。私は始めからそれを望んでいない。
自分の実存の問題について理解して欲しいわけでも「自分探し」でもない。
最初からあらかじめ最底辺労働を担う女性にむけて制作され、自分自信もその当事者として、そして母も、祖母もこの中では肉親というよりも「同志」として対象化したくて登場してもらった。
予想通り女性の反応がいい。なぜ語りが必要なのかがあるカテゴリーの人々には伝わらない。マジョリティーに伝わらない手法に苛立たれる事、キレられることも多々ある。この映画はほとんどが女の愚痴だからだ。延々と続く「愚痴」に対しての反応でその人の歴史もみえてくるかもしれない。 今回の上映でも一部の男性は途中で我慢できず携帯をいじったりしていた。でも、確実にある層にはその語りの必然性が伝わっている様だった
今回嬉しかったのはある男性に「よかったです」と言われ、その方のプライベートなお話しも少し聞けた事でした。届けたい人と想いを共有できることの至福を味わった数時間でした。(根来祐)
映画の中の根来さんは電車に乗って帰るようで、でも遠くに行くようなかんじで、母や祖母に会いに行く。「娘」「お母さん」「おばあちゃん」という立場で、それぞれの世代の仕事、生きかたを語るとき、対立したり共感したり。母娘の閉ざされた関係の中で、ゴツゴツと窮屈なこと、わたしもあるなーと思いました。でも、ビデオを撮る「わたし」や、描いた絵を眺めて語るふたり、またお茶を点てあう3人の場面は、横並びの安心できるすがたのように見えました。それは、仕事じゃなく、家族でもなく、それぞれの「わたし」として手放さないことがある。このことを守るには、「家族のために生きて幸せだ」と公言していかなければならないのか?
映画の後に、根来監督が個人史をみせたかったわけではない、と話していたように、これは女性の多くの人たちが感じている母娘関係で、さらに、「わたし」がない「母」という立場に挑む「娘」についてだったように感じました。また、フリートークでは、同じ女性の立場の人から、「映画の中では男の人がひとりも出てこないのに、『お父さんは、』と『母』が語り、『おじいちゃんは、』『お父さんは、』と『祖母』が語って登場していた。」というコメントがありました。そのように、一人称がわたしではなく「お母さんはね」「お父さんがね」と、「わたし」でいることを奪われていること、それが社会では自明とされて、それどころか美しく正しいことのように語られていることは多いと思います。でも、この映画ではそれをたんたんと見据えて、根来監督の「わたし」を通して、女の、わたしは誰か?あなたは誰か?ということに向かわせてくれているように感じました。「母」、「妻」、「恋人」でもなく、女の人がひとりで尊重される空間が、公園にどれほどあるかということを考えていきたいです。(いちむら)





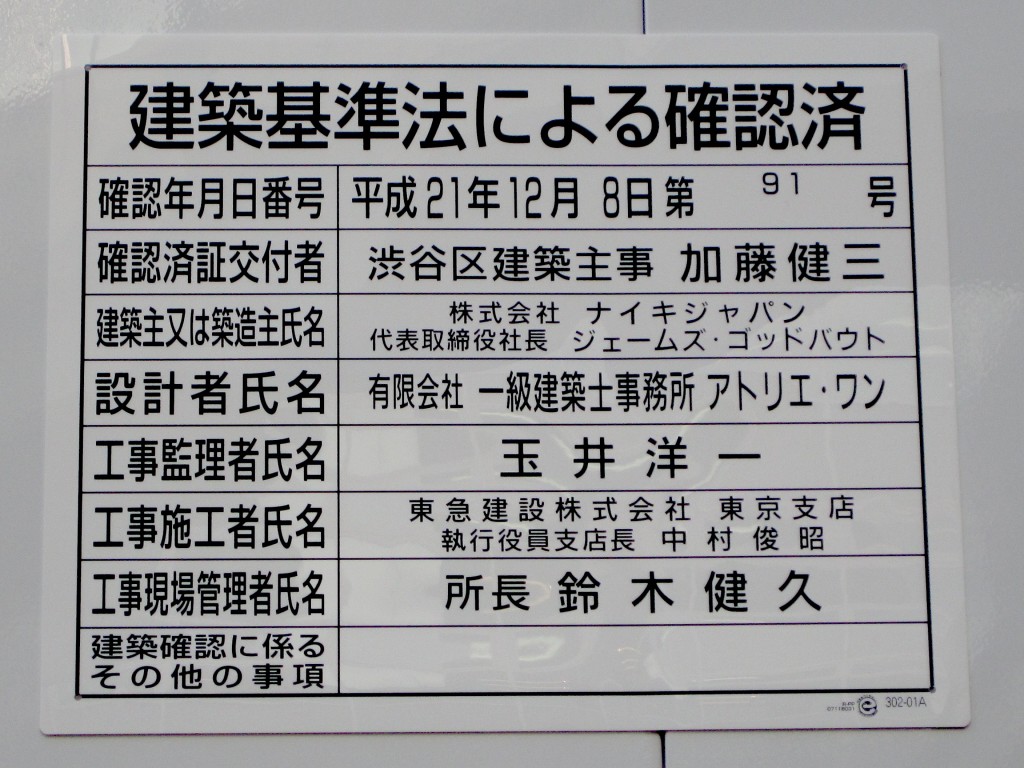






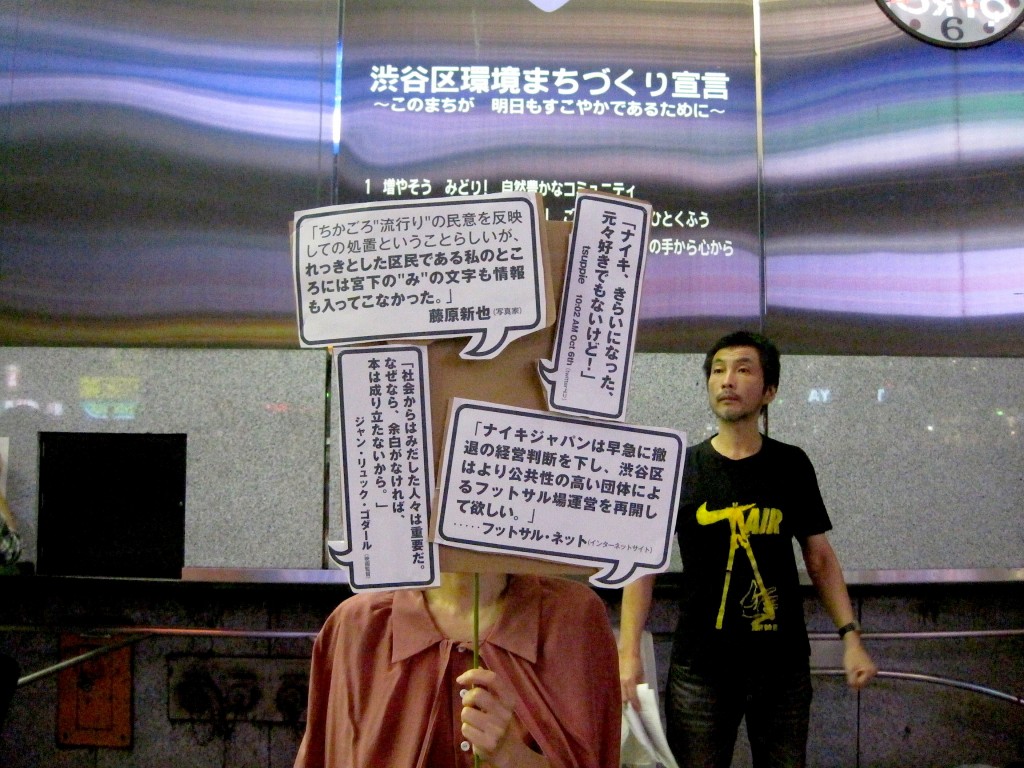
TrackBack URI